おはようございます♪
2020年のお月見に作った名古屋風お月見団子の紹介です。
10月1日は中秋の名月=お月見でした。下の子が保育所でお月見の制作をしたりお月見の会をやってきて、お月見の日=お団子が食べれる日、という認識でずっと楽しみにしていました。
お月見当日は平日だったので凝った献立はできなかったのですが、お月見団子だけは作ってみました。今年は、名古屋では一般的なしずく型お月見団子を作って、はさみでちょきちょき切るだけでできる耳を作ってうさぎ型にしてしてみました。

お月見団子と言えば、白くて真ん丸でピラミットのように積み重なったものが一般的なお月見団子ですよね。
でも愛知県(名古屋周辺)ではしずく型で、3色(茶色、ピンク、白)のお月見団子が一般的なんです。スーパーでもしずく型のものが売っています。Pasco(敷島製パン/名古屋本社)からも販売されています。なぜしずくの形なのかというと、「里芋」の形だそうです。お月見の日の中秋の名月は「芋名月」ともいわれ、お月見は秋の収穫を祝う行事であり、里芋をお供えしていたことから、お月見お団子が里芋型(しずく型)になったという説があります。
そんな里芋型の名古屋の月見お団子を、お月見といえばうさぎということで、うさぎ型にしてみました。はさみで切るだけなので意外と簡単です。
お月見団子は基本的に上新粉(米粉)のみで作ると思いますが、上新粉だけだと時間が経つとこっつりするので、少し片栗粉を入れてもっちりさせました。また、フルーツポンチ等に入っている白玉団子とは違い茹でるのではなく「蒸す」のがポイント!むっちりした食感の美味しいお団子になります♪
うさぎ型の名古屋風お月見団子の作り方
材料(20個分くらい)
- 上新粉(米粉) 150g
- 片栗粉 30g
- 砂糖 30g
- お湯 適量
- 食紅 少々
作り方
- ボウルに上新粉、片栗粉、砂糖を入れて混ぜておきます。お湯を沸かしておきます。
- お湯を少しずつ入れて、混ぜながらまとまるまで様子を見ながらお湯を加えていきます。入れすぎ注意!

- 3つに分けて、1つにピンク(赤)の食紅を入れます。※茶色は最初から分けて砂糖を黒糖にして(上新粉50g片栗粉10g黒糖10g)茶色にするのですが、今回は茶色の食紅があったのでそれで作っちゃいました。

- ピンポン玉くらいに丸めて、端っこを棒を作るようにころころ転がして伸ばし、”しずく型”に成形する。

- キッチンバサミで2か所チョキチョキしてうさぎの耳を作る。意外と簡単。


クッキングシートを敷いた蒸し器の上に並べます。
- 20分ほど中火で蒸して完成。

つやつやでぷりぷりです。




3匹並べると可愛い。時間が経ってもこちこちになりにくくもっちりしたお団子です。ちょっと時間おいて、こつっとして乾燥した方がお月見団子っぽくて美味しいです!
お月見の夕食献立
- 肉団子甘酢あん
- さつまいものレモン煮
- 月見うどん うさぎかまぼこ乗せ

夜ごはんのお月見メニューは簡単にしました。
お団子はそのままでも若干甘いですがきなことあんこをつけて食べました。

月はお庭から見えず、玄関から出ると見えました。お月様を見ながら団子は食べられなかったけど、お月見の日に団子を食べるという行事をみんなで一緒に楽しめて良かったです。
そういう行事をしっかり子供に教えてくれた保育所にも感謝です♪

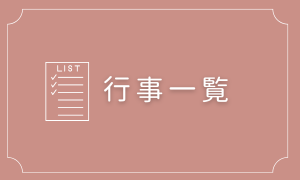
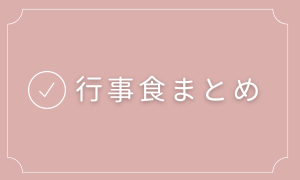
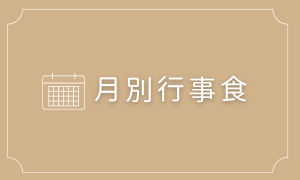
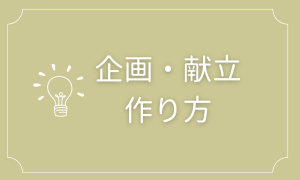










コメント